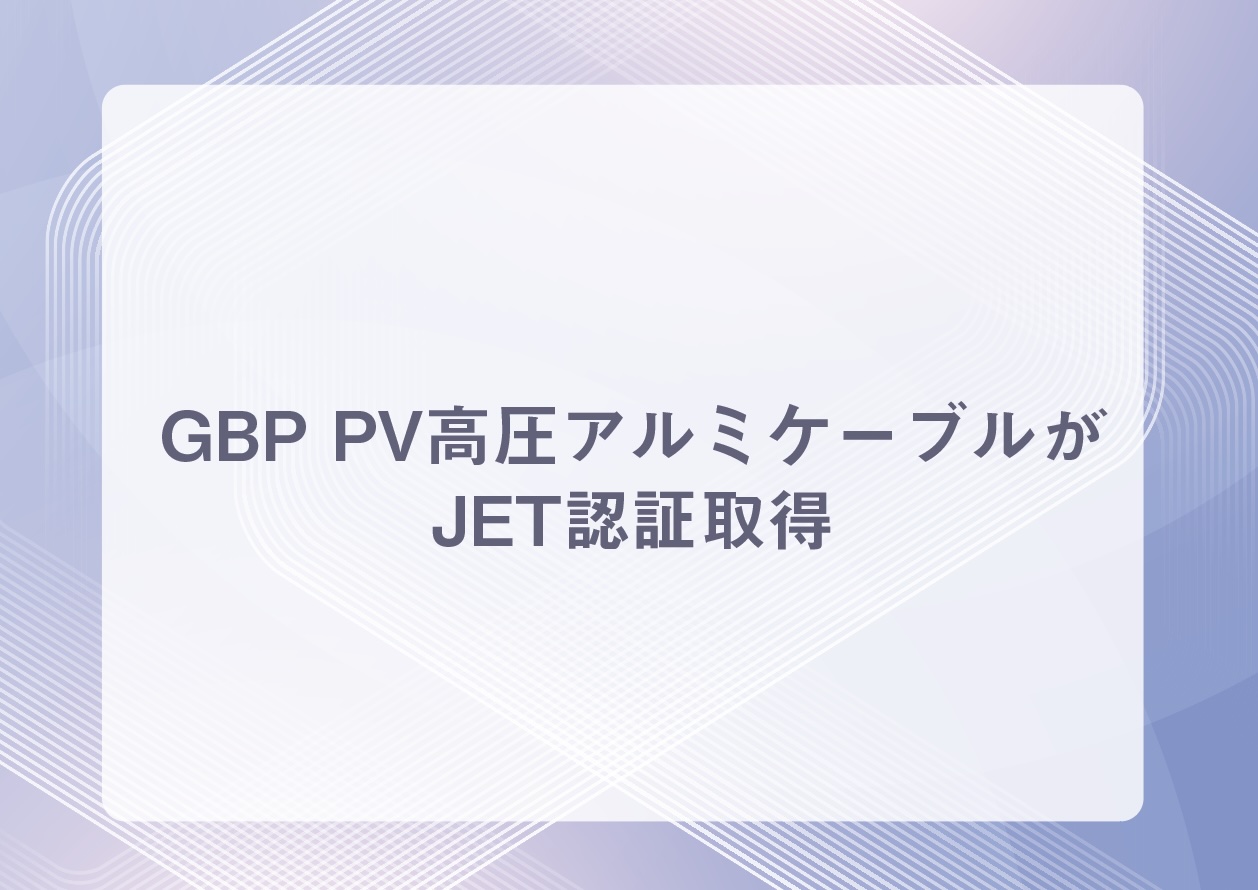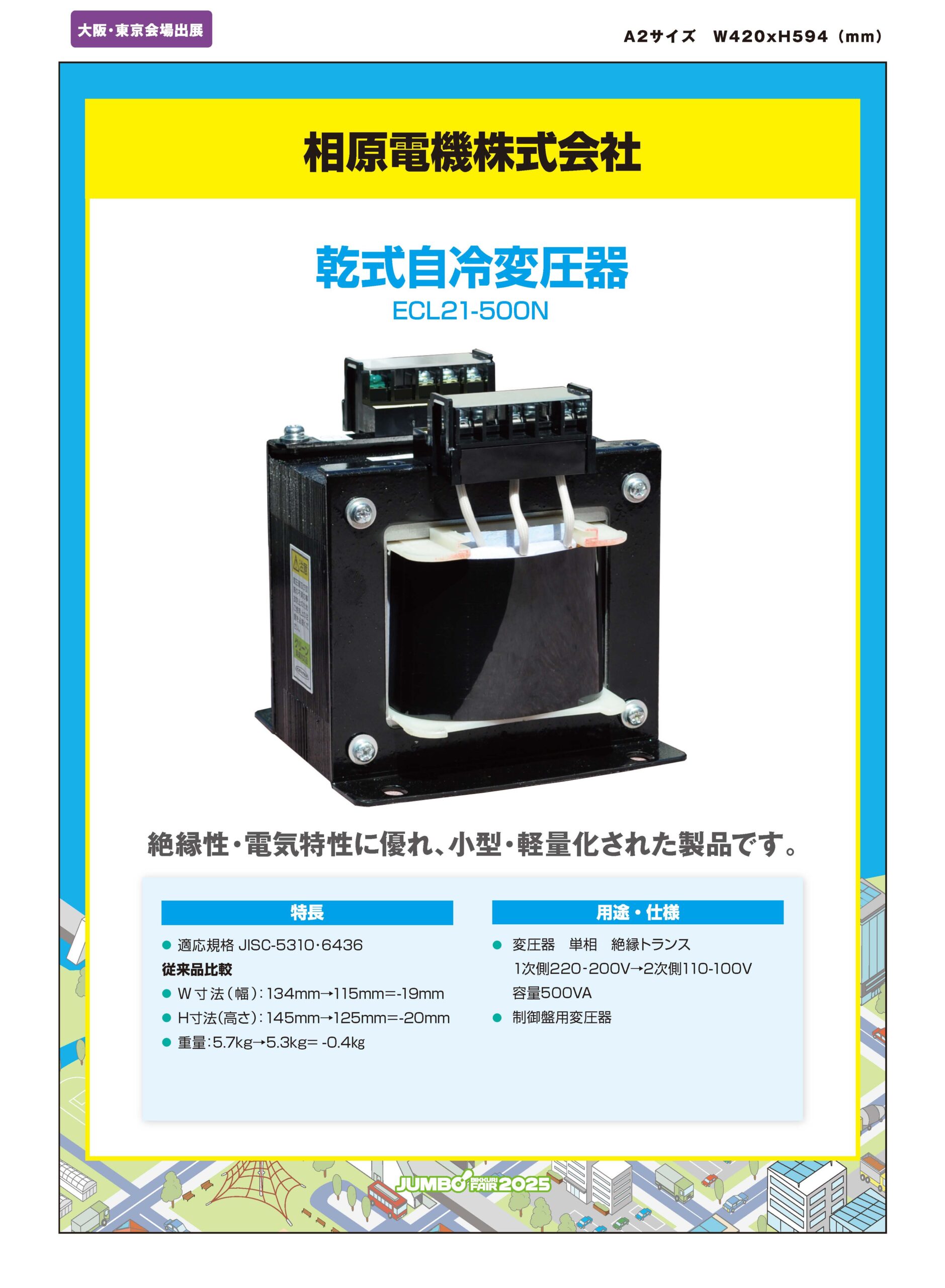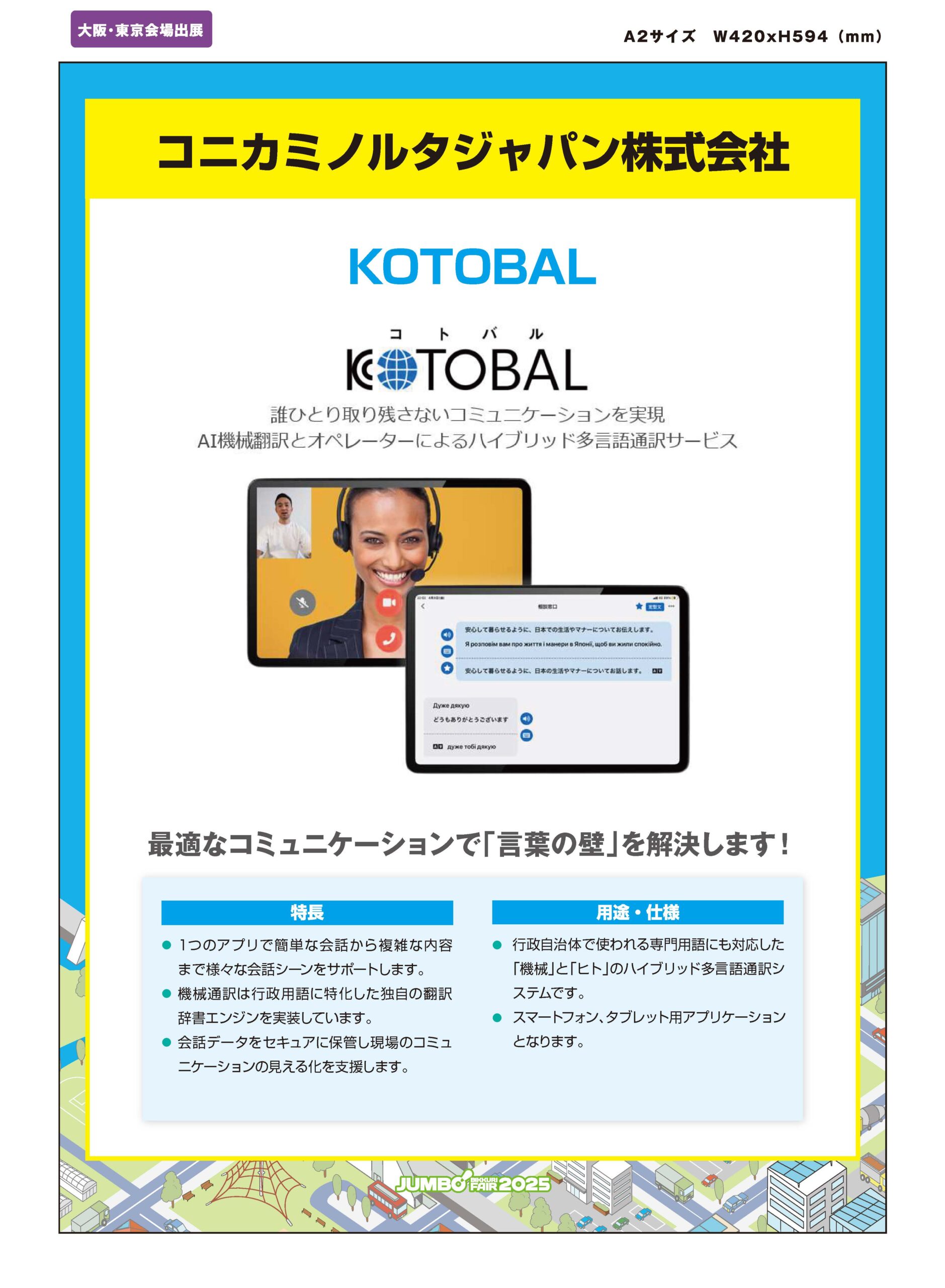いよいよ身近な存在になってきたロボット。

人間そっくりなアンドロイドの研究が進んでいるようですが、今、私たちの生活に身近なロボットといえば、ファミリーレストランなどで活躍している配膳ロボットでしょう。「ルンバ」に代表されるロボット掃除機もすっかり定着しましたが、あれは姿形がロボットっぽくないので面白みに欠けるというか。その点、最近よく見かける配膳ロボットは子どもの背丈くらいあって、顔もあり、表情豊かです。顔はネコだったりしますけれど。そして、注文した人のところへちゃんと料理を運ぶだけでなく、「ご注文ありがとうニャ」や「通してほしいニャ」などとしゃべります。頭をなでてあげると「気持ちいいニャ~」といって喜ぶので試してみては。ただし、なですぎると「さわりすぎニャ!」といって怒られます。本当ですよ。
そんな愛らしいネコ型配膳ロボットは、中国の大手ロボットメーカーであるPudu Roboticsが開発した「BellaBot(ベラボット)」というそうで、4.5時間の充電で12時間稼働し、バッテリーを交換すれば24時間稼働も可能とのこと。気になるお値段は、インターネットで調べた限りではざっと300万円前後。新車が買えますが、レンタルだと月額5~10万円程度。まさにネコの手も借りたい飲食業界にあって、月給5万円で24時間不眠不休、不平不満もいわずに働いてくれます。ファミレスは将来、ロボットだらけかもしれません。
ちなみに、ソフトバンクロボティクスが開発したヒト型ロボット「Pepper(ペッパー)」くんは今どうしているかというと、在庫が十分に確保できたため生産を一時的に停止しているそうですが、誕生から10年が経過し、集客や接客、教育、介護など、活躍の幅を広げています。ペッパーくんも動力源はリチウムイオンバッテリーで、本体価格19万8000円とリーズナブルです。
アラレちゃんの動力源はロボビタンA。
思えば、昔はロボットといえばSFの世界。映画や漫画だけに登場する架空の存在でした。その元祖といえば『鉄腕アトム』でしょう。21世紀の未来を舞台にロボット少年が活躍する物語を、漫画の神様・手塚治虫は今から70年以上も前に描きました。日本には産業用ロボットさえまだない時代です。名前からわかる通り、アトムの動力源は原子力ですが、時代の変化とともに燃料電池に変わったようです。
1969(昭和44)年に誕生し、今や世界中で愛されているネコ型ロボットの『ドラえもん』も原子力エネルギーで動いていましたが、現在は何を食べてもエネルギーになるのだとか。もちろん大好物は、どら焼きです。
1970年代は特撮テレビ番組が爆発的なブームを巻き起こしました。中でも画期的といえるロボット(人造人間?)が『キカイダー01』のイチローです。はい、『人造人間キカイダー』のジローのお兄さんです。赤いギターを弾いて現れる弟のジローに対抗して、白いトランペットを吹きながら(そこそこ長い演奏で)登場するイチロー兄さんは頭部に太陽電池を搭載しており、太陽の光をエネルギーに変えて変身し、そしてハカイダー部隊と戦うのです。つまり時代を先取りした太陽光発電なのだ! だから曇りや雨の日は弱いのだ……。
ロボットは男性ばかりではありません。忘れてはいけないのが、漫画『Dr.スランプ』のアラレちゃんです。テレビアニメでは『Dr.スランプ アラレちゃん』というタイトルでしたが、ウンチを持ってキーンと走るアラレちゃんは、自称・天才科学博士の則巻千兵衛がつくったロボットです。動力源は“ロボビタンA”で、その原料は海水なのだそう。
人間がロボットを助ける時代?
強くてカッコイイ正義の味方。困ったときに助けてくれる人間の友達。そんなイメージがこれまでのロボットでした。ところが現代は、独りでは何もできない“弱いロボット”が注目されているようです。
例えば、昔話の「桃太郎」のお話をしている途中に「えーと、何が流れてきたんだっけ?」と逆に尋ねてしまうロボットや、ゴミを見つけてゆっくり近づいていくものの自分では拾えないロボット、モジモジしてなかなかティッシュを配れないロボットなど、ニュースで取り上げられたりしているのでご存じの人も多いでしょう。豊橋技術科学大学の岡田美智男教授が率いるICD-LABの研究です。このような、思わず手助けしたくなる弱いロボットが人間の優しさを引き出すといいます(参考:「ICD-LAB 豊橋技術科学大学」ホームページ他)。
ロボットの動力源と同じように、ロボットの役割もまた、時代とともに変わってきているのかもしれません。