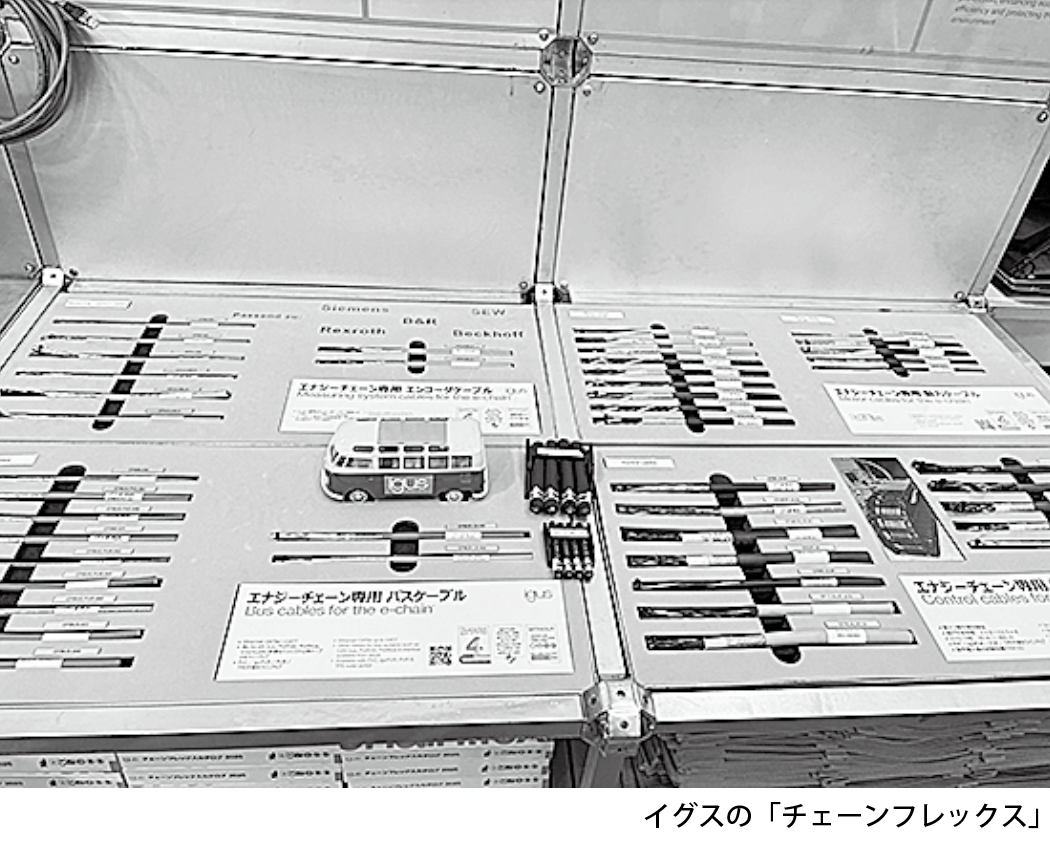若い二人にはまぶしかった裸電球

「あのころ二人のアパートは裸電球まぶしくて」と歌ったのは、昭和のフォークグループ「かぐや姫」。初期のグループ名は「南こうせつとかぐや姫」です。この『赤ちょうちん』という曲は、同じく若い男女の同棲生活を題材にした『神田川』に続く“四畳半三部作”の第2弾で、1974(昭和49)年にリリースされました。ちなみに第3弾は『妹』です。どれも泣かせる名曲です。――「なんの話?」と、平成生まれのナウなヤングは思うでしょうけれど、とにかく昭和時代は、お金のない若者の住まいといえば四畳半のアパートで、その部屋の照明器具といえば裸電球と決まっていたのです。誰が何といおうと、そうなのです。裸電球とはつまり、むき出しの白熱電球のこと。いま見れば薄暗いあの電球が、あのころの若い二人にはまぶしかった……そう、青春の輝きだったのです!
つい熱くなってしまいましたが、今の若い人たちもテレビか何かで見たことがあるのではないでしょうか。古い住宅の天井からぶら下がっている白熱電球には小さな傘がかぶさっていて、スイッチも電球の差し込み部(ソケット)に付いていました。もちろんオン・オフのみ。それだって電球も電力も貴重な時代です。二間ある家などは長い電源コードで部屋から部屋へ傘ごと持ち運んだりしていました。
日本の照明は明るすぎるのか
若者が裸電球の下でつつましやかに暮らす一方、蛍光灯も昭和の中頃から一般家庭に普及し始めていました。電球の照明と同じく吊り下げ式で、プラスチック製の四角い和風の傘がトレンドでした。傘の内側には丸型蛍光灯が2灯設置されていて、部屋の隅々まで照らすその白い光に初めはみんな大層驚いたといいます。
ちなみに、外国人から見れば日本の住まいは明るすぎるそうです。確かに、欧米などの家庭は現在でも白熱灯や電球色の照明が多いようで、また、大きな明かりで全体を照らすのではなく、間接照明を利用して柔らかな光を演出するのが主流のようです。ホテルなどに宿泊すると天井に照明器具がなくて、暗いと感じた人も多いのではないでしょうか。住宅だけでなくオフィスもスーパーマーケットもコンビニエンスストアも、日本は確かに明るいと思います。
日本人はなぜ、こうこうとした明かりを好むのか。これには幾つかの理由や説があって、一つは、そもそも目が違うそうです。医学的なことはわからないので簡単に申しますと、青い瞳と黒い瞳の違い。日本人の黒い瞳はまぶしさに強いのだそう。欧米に日頃からサングラスを着用している人が多いのは、まぶしさに弱いということもあるようです。
もう一つ挙げると、日本人の白熱灯に対するイメージです。戦後、『赤ちょうちん』の時代よりももっと前、裸電球の下で貧しい暮らしをしていた日本人は少なくありません。従って“白熱灯=裸電球=貧しい”という印象が私たち日本人の深層心理にはあって、それ故に白く明るい蛍光灯の光を好むという説があります。いわれてみれば、そんな気がしないでもありません。ムーディーなレストランのほの暗い照明を、若い人ほど「落ち着く」と感じ、高齢な人ほど「落ち着かない」と感じる、と何かで読みました。明かりと一口にいっても、国や世代の違いによって捉え方はさまざまなようです。
時代を照らす明かり

稀代の発明王エジソンが1879(明治12)年に開発したとされる白熱電球によって、明かりは火から電気の時代に入りました。その約60年後の1938(昭和13)年にアメリカで蛍光灯が登場し、さらにその約60年後の1996(平成8)年に白色LEDが登場しました。そして、2023(令和5)年の「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」で、一般照明用蛍光灯の製造および輸出入を2027(令和9)年末までに段階的に廃止することが決定しています。現在はLED照明が主流ですが、将来また新たな明かりが誕生するのでしょう。そのとき、その光は、どんな時代や暮らしを照らし出すのでしょうか。