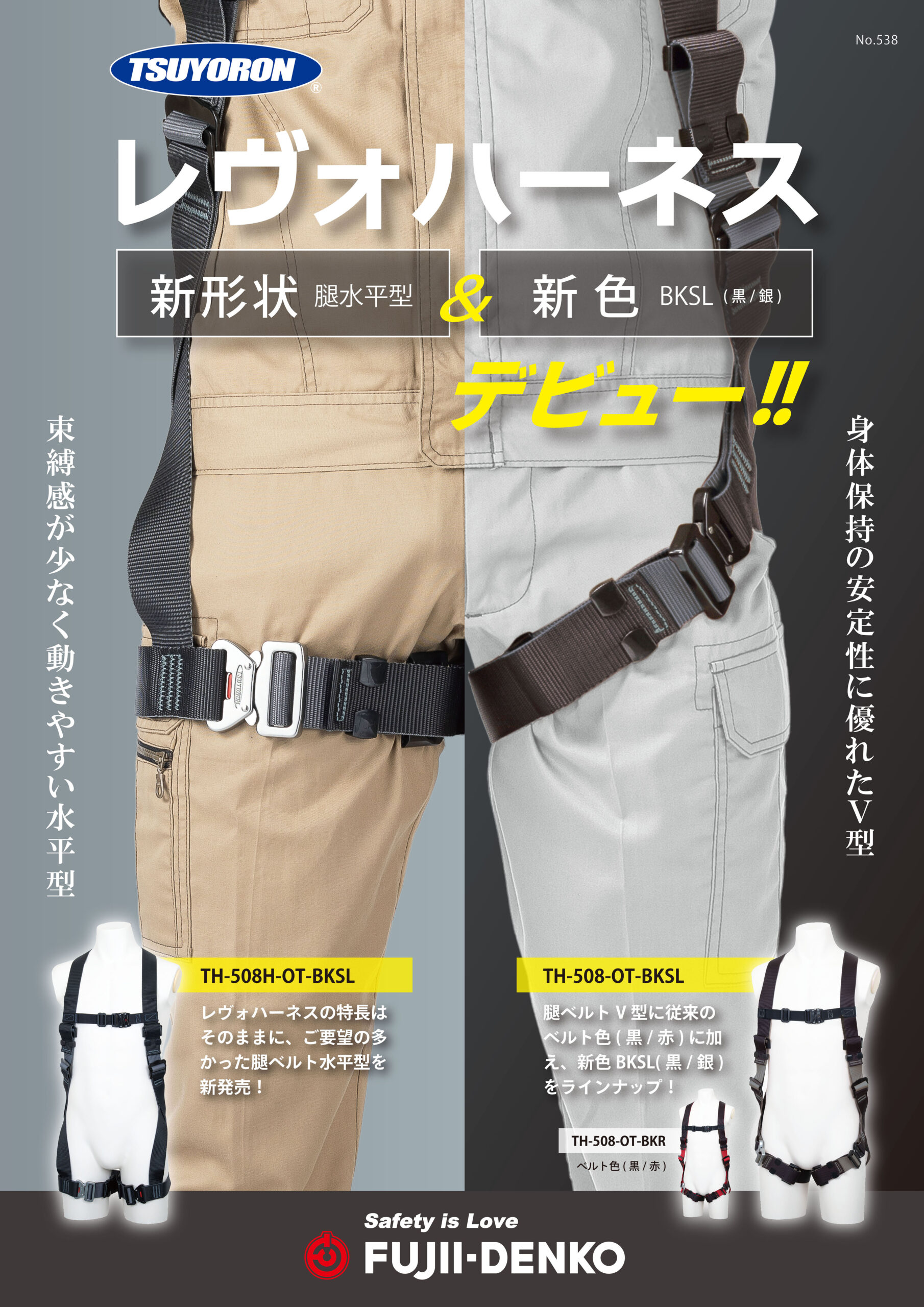うどんつゆの色は、なぜ東西で違うのか?
「ほんまに真っ黒けやん!」と、初めて東京でうどんを食べた関西人は驚きます。
「ほんとに薄いんだ!」と、初めて大阪でうどんを食べた関東人も驚きを隠せません。
東西のうどんつゆの違いはもう有名ですが、百聞は一見にしかず。実際に食べてみると、ちょっとしたカルチャーショックを味わうことができます。

関西のうどん
「うどんつゆ」と書きましたが、関西では一般的に「うどんだし」といい、昆布とかつお節や煮干しから取っただしの風味を生かし、醤油や塩などで味を整えます。色の淡い薄口醤油を用いるため、透き通った黄金色になります。
 関東のうどん
関東のうどん
一般的に「うどんつゆ」という関東では、主にかつお節からだしを取り、濃口醤油などでしっかりした味に仕立てます。色の濃い醤油を使うため、不透明で黒っぽい色になります。
なぜ、関東はかつお節に濃口醤油で、関西は昆布に薄口醤油なのかは、東西における食文化の歴史や気候風土の違いにまで話が及ぶので、それはさておき。日清食品の「どん兵衛」も東西で味付けを変えているのはよく知られた話で、その境界線は岐阜県の関ヶ原なのだそう。安土桃山時代、徳川家康率いる東軍と石田三成を中心とする西軍が激突した天下分け目の戦いの地は、 “味の分け目”でもあったのです。
他にもまだまだ、いろいろあります。たとえば卵焼きは、関東は甘い味付け、関西はだしの効いたしょっぱい味。いか焼きは、関東は姿焼き、関西は粉もん。うなぎの蒲焼きは、関東は背開き、 関西は腹開き。中華まんは、関東は肉まん、関西は豚まん。おでんは、関東ではちくわぶやはんぺんが人気、関西では牛すじや厚揚げが人気。関西では昔、おでんのことを関東煮(関東炊き)と呼んでいました。
電気の周波数は、なぜ東西で違うのか?
もう一つ(というか本題ですが)、種類は同じなのに東西で異なるものがあります。――そう、答えは電気の周波数です。
「3.141592……」
それは円周率。周波数とは、決まった時間内に繰り返される波の数を指し、Hz(ヘルツ)という単位で表されます。電気以外にも音響工学や情報工学、自然科学、医学など、多様な分野で用いられています。
周波数の違う2種類の電気が使われている日本は世界でも珍しい国だそうです。“電気の分け目”は関ヶ原よりもう少し東、静岡県の富士川と新潟県の糸魚川あたりを境に東側が50ヘルツ、西側が60ヘルツです。ただし、境界周辺には50ヘルツと60ヘルツが混在している地域もあります。
目に見えない電気の周波数を私たち生活者が意識するのは、いうまでもなく電化製品です。周波数が合っていない電化製品を使うと故障や火災の危険性もあるので注意しなければなりません。二つの周波数に対応している共用の機種は全国どこでも使用できますが、東西どちらか専用であれば、たとえば富士川をまたいで引っ越す際は部品を交換するか、製品自体を買い替える必要があります。
このような不便がなぜ存在するかというと、その昔、東京ではドイツ製50ヘルツの発電機を、大阪ではアメリカ製60ヘルツの発電機を、それぞれ輸入して電気をつくり、それが全国に広まって現在に至るから。わが国の産業が著しく発展した明治後期のことです。どこかのタイミングで統一できなかったのかと思ってしまいますが、それ以前はさらに125ヘルツや133ヘルツなどもあり、東西どころか地域や発電所によってまちまちだったとか。周波数を一つにすることは何度か検討されましたが、費用の問題や、整備期間は電気の供給が滞るといったことから見送られてきたようです。
ともあれ、東と西が何かにつけて違うのは面白いものですね。