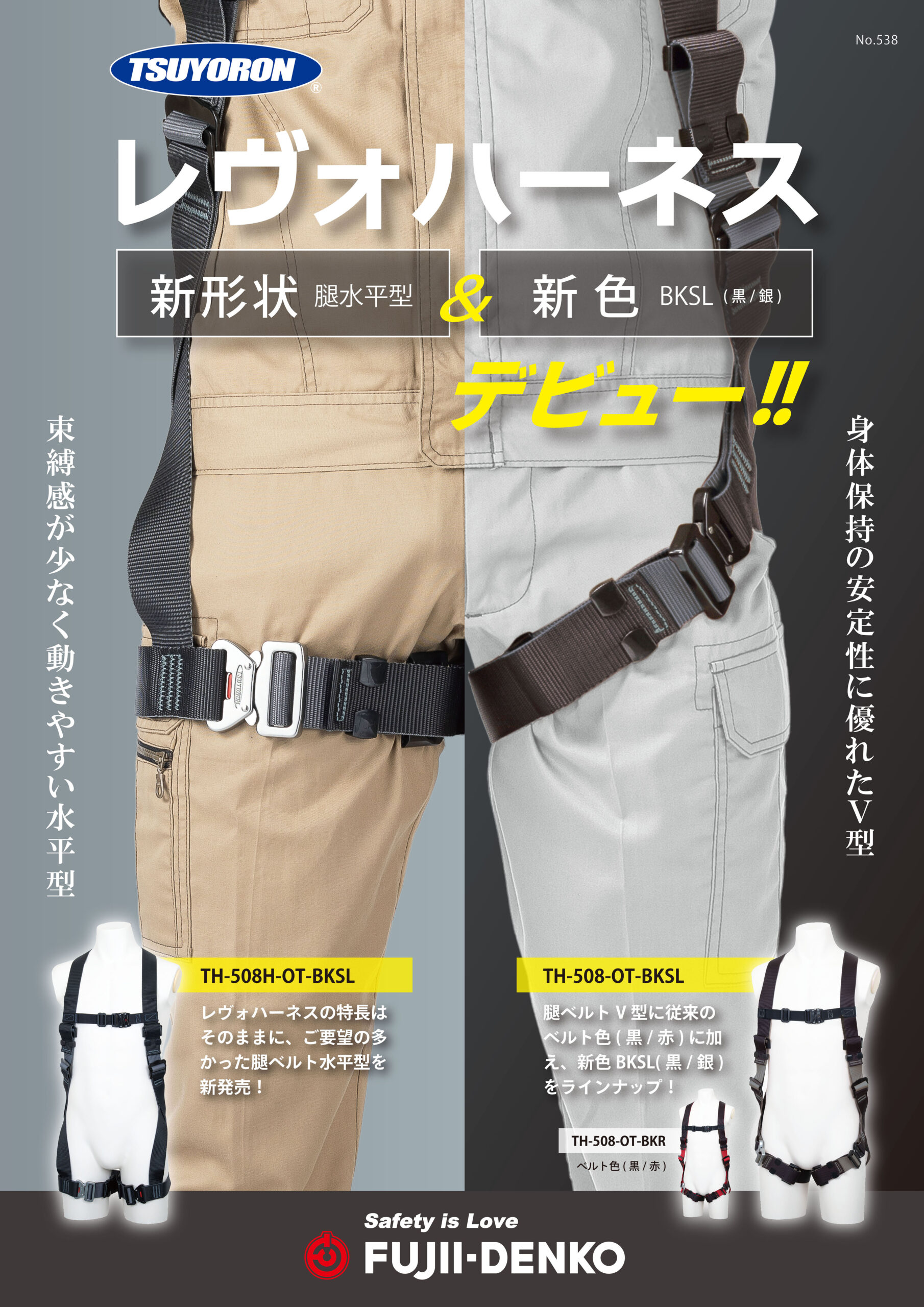彼女のおとうさんが出る昭和の電話

近頃は小学生だってスマートフォンを持っています。おじいちゃんおばあちゃんもスマホを使いこなしています。1人1台電話を携帯していて、いつでもどこでもつながります。すごい時代になったものです。
昔は有線の固定電話しかありませんでした。公衆電話は赤い電話機(後に電話ボックス用の青電話や100円硬貨が使える黄電話も登場)、家の電話は黒い電話機と決まっていました。黒電話は、電話番号のアイコンで今も見かけるあの形です。指で回すダイヤルと受話器が付いているだけで、ナンバーディスプレイも留守番電話機能も音量調節も何もないシンプルさ。ただ、どこの家もなぜかレースのカバーを被せていました。
ガールフレンドの家に電話をしても、彼女が出るとは限りません。
花子さん「じゃあ10時ね。バイバイ♡」
太郎くん「うん、電話するよ。バイバイ♡」
花子の父「花子、なにをソワソワしているんだ?」
(家。花子の様子を見て状況を察する父)
SE: ジリリリリーン!
(電話が鳴る。間髪を入れず受話器を取る父)
花子の父「どちらさまですかっ!」
太郎くん「た、太郎と申します。は、花子さんをお願い……」
花子の父「娘はもう寝ましたぁー!」
SE:ガチャン!(乱暴に電話を切る音)
SE:ツー、ツー、ツー(受話器を握りしめて呆然とする太郎くん)
厳しいお父さんがいる家庭は、こんな感じでした(笑)。
日本に初めて一般的な携帯電話が登場する1987(昭和62)年以前の話ですが、それよりもっと前の電話機は直通ですらなかったというから驚きです。
手作業でつないでいた明治の電話

若い人もテレビドラマか何かで見たことがないでしょうか。木箱のような形の機械が壁に掛けられていて、その機械に付いている小さいラッパのような物を耳に当てながら、機械の側面のハンドルをぐるぐる回している人の姿を。あれが昔の電話機です。「デルビル磁石式壁掛電話機」といい、1896(明治29)年から1965(昭和40)年頃まで約70年間も使われました。
でも、電話機なのに話したい相手にはつながりません。そもそもダイヤルが付いていません。ハンドルをぐるぐる回すと発電して、電話局の交換台につながる仕組みです。なんだか、すごいですね。そして、つながる相手は電話交換手。今風にいえばオペレーターです。その人に「もしもし、花子さんをお願いします」とか「何番につないでください」などと伝えると、花子さんの家の電話に回線をつないでくれるのです。なんと手作業で。しかも、つないだだけでは花子さんが気づかないため、ベルまで鳴らしてくれます。話し終わると、またハンドルをぐるぐる回して電話交換手に伝え、それを受けて電話交換手は回線を切ります。詳細もし違っていたらすみません。概ねこのような手順だったようです。
これまたテレビか何かで見たことがないでしょうか。ヘッドホンを装着した大勢の女性が大きな機械の前にずらりと座っていて、めいめい何やら話しながら、回線の先端のプラグを機械のジャックに差し込む姿を。あれが電話交換手です。海外からやってきた当時の花形職業で、対応の柔らかさから女性が多く採用されたそうです。
グラハム・ベルもびっくり
日本で初めての電話サービス事業は1890(明治23)年、東京・横浜間に電話線が引かれて始まりました。しかし、加入費用や通話料金が高額だったため、電話を置けるのは一部の裕福な家庭に限られており、当初の加入者数は東京と横浜を合わせても200世帯に満たなかったといいます。
ちなみに、「KDDI」のホームページによると、ハンドルをぐるぐる回して電話をかけていた1897(明治30)年頃の、東京・横浜間の通話は5分で15銭。現代の貨幣価値に換算すると2250円相当だとか。まだ、ほとんどの人の連絡手段は手紙でした。
グラハム・ベルが電話機を発明してから約150年。今、日本ではほとんどの人がスマートフォンを持っています。いやはや、すごい時代になりました。